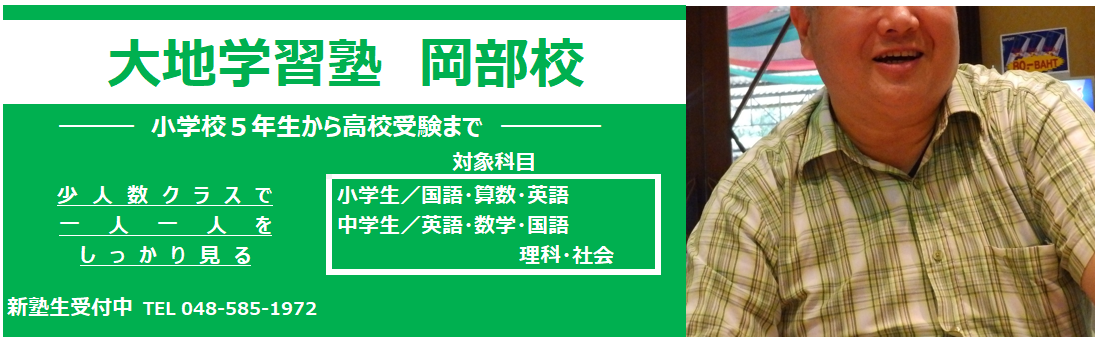こんにちは。晴れたり雨が降ったりを繰り返しながら、秋がどんどん深まってきたようです。
つい二週間前までは「まだ半袖で大丈夫」と思っていたのに「もはや長袖シャツ1枚では寒いな」と感じるまでになってきました。
生徒のみんなも体調管理には気を受けてほしいところです。
さて「抽象的な思考力強化のために」も二回目です。
今回は前回簡単にご紹介した当塾の漢字学習シートの改定とそれによる漢字学習の強化についてお話いたします。
前回、私は塾の漢字学習を大幅に改定する理由として以下の2点を上げました。
1.ここ数年で明白になってきた生徒さんの抽象的な思考力の低下傾向
2.大学入試改革、それにつながる高校入試の国語の問題の高難度化への対応の必要性
では、それぞれについて考察してみます。
まず「1」についてですが、これは「最近の小学校の高学年生、中学生は大人が読む文章を読む機会が減っている」ことが大きな原因ではないかと考えます。
「20年前に比べて4分の1の家庭が新聞を購読していない」というデータがみられる等、大人さえ「かたい」文章を読まなくなっていることからも分かります。
では、学生だけでなくみんながその分何をしているのかといいますと、SNSやLINEなどの極短い文のやり取りが多くなっているというのが実情ではないでしょうか。
これらのメディアは「気楽にコミュニケーションが取れる」という点ではよいのですが、相手を説得するための理論的な文章展開をすることには向いていないようです。
まして「うん」「ああ」「マジ~?」などのやり取りだけでは、抽象思考や論理的な文章展開力を育成するのは困難を極めるでしょう。
こうなると国語の選択問題で「なぜその答えを選んだのか?」という質問に対し「何となく」としか答えられない生徒さんが続出するのは当然かもしれません。
次の「2」についてですが、こちらは過去の当ブログでも何回か記載しましたように「埼玉県の公立高校入試の国語の問題は、過去10年で難度が上がっている」のが明白になっているからです。これは15年ほど前には平均の正答率が60%台後半だったのに対し、ここ数年は50%台前半に落ち込んでいることからも認識できます。
このような動きは記述式問題を出題する2020年度の大学入試改革に合わせた、高校入試問題の「進化」と考えられますが、同時にこの高難度化に「対応できる人」と「対応できない人」がはっきりとしてきました。
この二者で大きな問題となるのは「対応できない人」のほうであるのはもうお分かりかと思います。そしてその「対応できない人」は、すでに記載した「抽象思考が苦手」「論理的な文章展開が不得意」な人であるのです。
当塾の漢字学習強化の方針はこの点を考慮して進めていきます。もちろん漢字学習だけでは「抽象思考強化」「論理的文章力アップ」にはダイレクトにつながることは少ないと思われますが、四字熟語・対義語・類義語までを含めた語彙力の強化は、そのベースになるものと考えています。
そして、その上で生徒のみんなにはあることに取り組む様に声をかけています。
それについては次回お話ししたいと思います。
それでは本日はこの辺で失礼します。