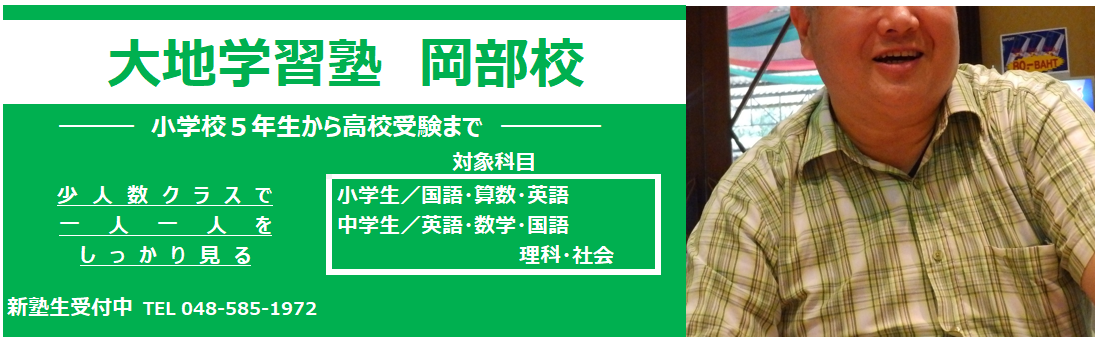こんにちは。
「公立高校入試の最終倍率も出た」
「この週末で最後の追い込み・仕上げをしよう」
という受験生も多いでしょう。
まずは
「体調管理」
「生活のリズムを保つ」
を優先して、入試までを過ごせるといいですね。
さて「最終倍率は下がる」の最終回です。
それは
Ⅲ.募集定員を超えて合格者を出すケースがある
という事です。
どういうことなのか?
これは公立高校入試の仕組みを考えると分かりやすいと思います。
公立高校入試合否判定の基本的な資料は以下の通りです。
1.中学校の成績表(いわゆる内申書)
2.実際の入試問題の得点
3.面接・実技の結果(一部の高校のみ)
大雑把に言うと、これらを各高校ごとの「基準」によって配点し、合否を決めています。
私の経験では、大体の傾向ですが、普通科・進学校は実際の入試の得点を、専門学科の高校は内申書を重く見るようです。
さらに単純化すると、各高校所定の内申書と入試の割合の合計得点で、合格者は決まります。
さて、この合計点の上位から合格者を決めていくことになりますが、問題は
「最後の一人を決める時に、ボーダーライン上に複数の受験生が並んだらどうするのか?」
という事です。
たとえば若干、内申書がいいA君と、入試で高得点のB君が定員上で並んだら、
A君を合格としても、B君を選んでも、不公平になりますね。
「内申書+入試」の合計点は同じなのですから。
そこでこのような場合、各高校では原則として
「ボーダーライン上に並んだ人は、全員合格にする」
ようにしていると思われます。
過去には定員360名に対して、18名オーバーの合格者を出している高校もありました。
360名ということは9クラスですから、
各クラスに「ボーダーライン上」で生徒が、2~3名並んでいたという事になります。
さて、このように合格者を出すのはどのような高校なのでしょうか?
私が見ている限りでは、次のような高校にその傾向があります。
・ 難関の進学校
・ 倍率が高い高校
いずれも最後の一人がボーダーライン上に並びやすい状況の高校です。
ですから、こういった高校を受験する人は
「他の受験生はレベルが高いんだろうなあ」
「倍率が高いから受かる気がしない。落ちたらどうしよう?」と考えるよりも
「何としてもボーダーライン上にでも残ってやる!」
と考えて、入試までの学習に取り組んだ方がいいですね。
そこで、毎年私から全ての公立高校入試に挑む受験生に対の言葉を添えて、このテーマを終わりにします。